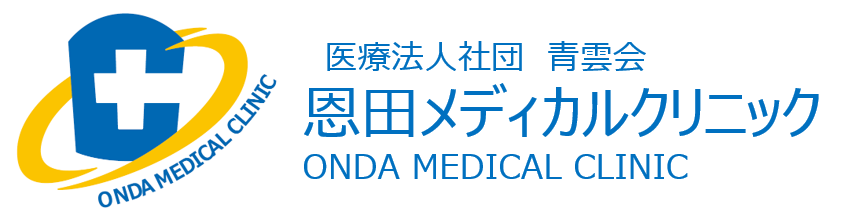2025年3月12日

3〜4月頃、特にひな祭りの時期に出回る桜餅、桜餅には関東と関西に違いがあるのをご存知ですか。
この時期になると昔義母に「これは桜餅じゃない・・・」と言われて驚いたことを思い出します。今回はそんな「桜餅について調べてみた」というお話です。
桜餅とは?
桜餅は小麦粉やもち米で作った桜色の生地であんを包み、塩漬けされた桜の葉を巻いた和菓子です。春の季語でもあります。関東風と関西風があり、共通点はどちらも桜の葉を使用している事です。
関東風の桜餅

関東風の桜餅は「長命寺(ちょうめいじ)」とも呼ばれ、今から約300年ほど前に隅田川の長命寺で門番の山本新六が桜の葉を塩漬けにしてお餅に巻いて売ったのが始まりと言われているそうです。小麦粉等をクレープ状に焼いた皮であんこを包んでいるのが特徴です。
関西風の桜餅

関西風の桜餅は「道明寺(どうみょうじ)」と呼ばれ、大阪の道明寺で初めて作られたそうです。道明寺はいつ頃・どのように・誰が誕生させたかは定かではないそうですが、関東風の桜餅を参考にして作られた、とも言われているようです。蒸したもち米を乾燥させてから引いた道明寺粉の皮の中にあんこを詰めたもので、つぶつぶ・もちもちとした食感が特徴です。関西風の桜餅は関東では、「道明寺」や「道明寺桜餅」と呼ばれています。
他の地方の桜餅は?

関東風の桜餅は関東地方の他に東北・北陸地方(一部除く)、長野県・山陰地方などで主流のようです。山陰地方はそれまで関西風が主流のようでしたが、松江藩の家老が江戸の長命寺を知り、地元のお菓子屋さんに関東風を作らせた事で広まったとされているようです。関西風の桜餅は西日本・九州・沖縄と北海道が主流のようです。(一部除く)北海道には江戸時代に日本海を経由して交易をしていたため広まったそうです。そのため東日本の中でも日本海側では関西風を食べる地域があるようです。関東風・関西風の他に伊豆の「長八桜餅」・鎌倉の「ひとひら桜餅」・島根雲南市の「みどりの桜餅」など、日本各地にご当地の桜餅もあるようです。
桜餅の葉は食べる?

桜餅に使われる桜の葉は「オオシマザクラ」という桜の葉で、桜の葉を塩漬けにしたもので抗酸化作用・抗菌作用があり、防腐の効果が期待できます。桜餅に桜の葉を巻くのは諸説あるようですが、桜の香りをつけたりお餅の乾燥を防いだりするためだそうです。桜餅以外にも桜の葉を加工してお菓子やお茶に入れて使います。桜の葉は食べて問題ありません。桜の葉をつけたまま食べるとお餅の甘みと葉の塩味が、はがして食べると桜餅そのものの味が楽しめると思います。
私が思う桜餅・あなたが思う桜餅

話は冒頭に戻り、私が義母に「これは桜餅じゃない・・・」と言われた・・・の部分、それは「道明寺だよ」でした。義母(と義父)は東京都出身、私の両親は関西と九州出身で食べてきたのは関西風でしたので、調べてきた通りの違いがあったというわけです。ただ、調べても言われても私の桜餅といえば関西風なので、実際そうなのか?と思い、デイケアスタッフ十数人と友人数人に関東風と関西風2種類の写真を見せて「あなたの思う桜餅はどちらですか?」と質問してみました。千葉・埼玉・福島など関東・東北出身の方の多くは関東風を選んでいました。
理由は・小さい頃からなじみはこっち・関西風は道明寺と呼ぶ・最近はお店で両方取り扱ってるけど手にするのはこっちとの回答でした。関西・北陸・両親が関西方面出身の方は関西風を選んでいました。「小さい頃からなじみはこっち」が一番の理由でしたがそれと同時に関東に出てきた当初は関西風は見かけなく探してもなかった、大変だったとも言っていて、それは私の母も同じことを話していました。またスタッフの中でも比較的年齢の若い方は、どちらも桜餅、桜餅をあまり手にしない、どちらも桜餅なのであまり気にしていない・・と、友人の中には、「桜餅といえば関東風の方だけど、今はどちらも買ってどちらも楽しむ!」と回答がありました。
私の両親の住む地域では関西風(道明寺)しか見かけないよ、との事でしたので、両方ある地域ならではなのだと思いました。色々と合点がいく結果となったと思います。あなたはどう思いますか。今回は関東と関西、桜餅の違いのお話でしたが、桜餅以外にも様々な違いがあり驚いた事がたくさんあります。また今後機会があればお話できたらと思います。
松戸市馬橋 恩田メディカルクリニック 厨房